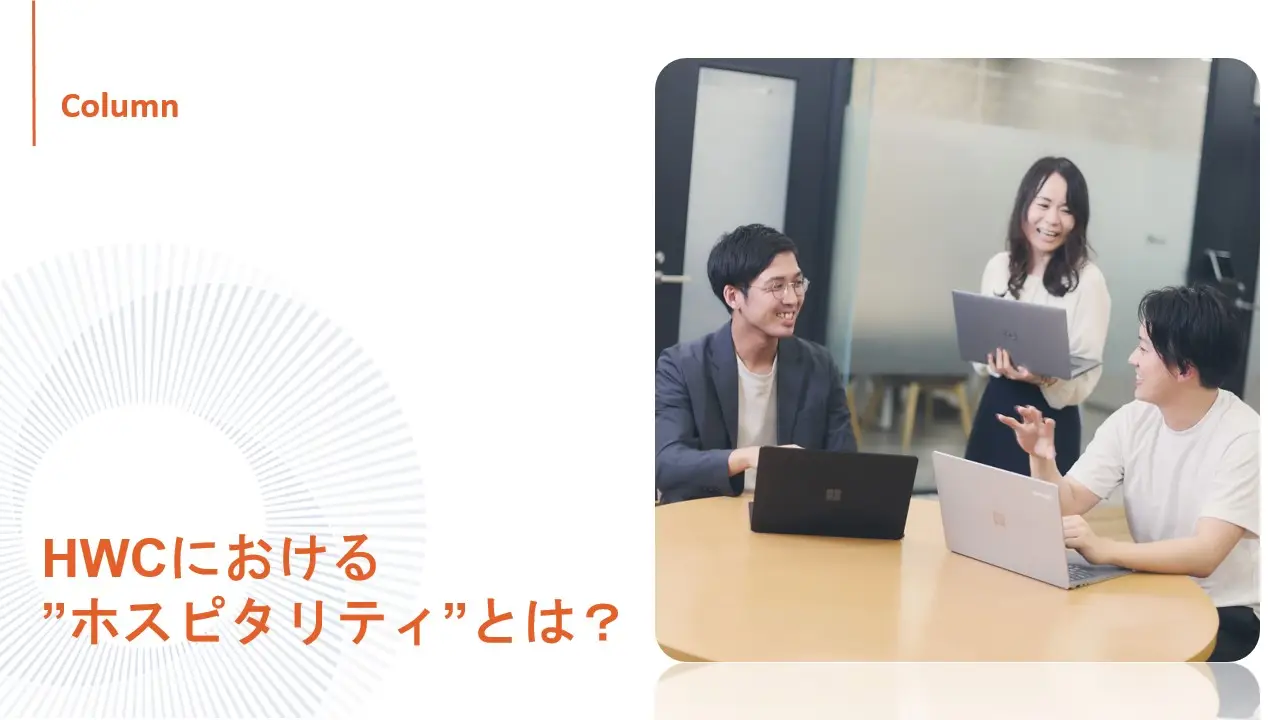提案で終わらない価値を。“社会実装”こそが私たちの存在意義【インタビュー】代表:加藤健司
2025.08.12- インタビュー

「AIでビジネスを変革する」というのは今や多くの組織が掲げる理想ですが、その実現には技術的・組織的な壁があることも多く、単なる提案では乗り越えられない現実も存在します。
そうした中、私たちヘッドウォータースコンサルティングは単なる提案にとどまらず、自らも「変革の当事者」としてお客様と正面から向き合い、“社会実装”というパーパスのもと、確かな成果を生み出すことを使命としています。
弊社代表の加藤は「新たなコンサルティングの形を追求し、社会の変革の先頭に立ち続けたい」と語ります。今回はその言葉に込められた思い、ヘッドウォータースコンサルティングが提供する価値、そして私たちが目指す未来について、ご紹介します。
プロフィール
加藤健司(かとう けんじ)
事業会社を経て2007年にIT業界へ転身。大手金融機関向け業務改善プロジェクトに複数参画後、2012年にヘッドウォータースへ入社。業務・ITコンサルティングに従事しつつ、2018年にコンサルティング部門を立ち上げ、2019年にグループ長、2021年に部長に就任。2019年以降はDX・AIコンサルティングに注力し、物流・建設・製造など多様な業界の大手企業を支援。2022年に、ヘッドウォータース100%資本で設立された新会社ヘッドウォータースコンサルティングの代表取締役に就任。

なぜ、技術者集団からコンサルティング会社が生まれたのか
──まず、ヘッドウォータースコンサルティング(以下、HWC)設立の背景について教えてください。
HWC誕生のきっかけは、親会社であるヘッドウォータースの組織変革にあります。AIを活用した課題解決が本格化する中で、単なる技術提供にとどまらず、より上流のビジネス課題に寄り添う必要性が高まってきました。社会全体が「AIを試す」段階から、「AIで本質的な課題を解決する」フェーズへと移行していたのです。
ヘッドウォータースは、当時も今も最先端の技術者集団として高い専門性を誇っています。しかし、技術を起点とするがゆえに、ビジネスの現場との間に一定の距離があるという課題も抱えていました。そのギャップを埋めるためには、お客様の事業の根幹に深く入り込み、技術とビジネスをつなぐ「より専門的な機能」が必要だと判断しました。
当初はヘッドウォータースの一部署としてスタートしましたが、コンサルティングという新たな機能を担うプロフェッショナルを迎えるには、分社化が自然な流れでした。コンサルタントとしての専門性を最大限に発揮できる組織と文化をゼロから構築することで、テクノロジーとビジネスの最前線で活躍したい人材にとって、最適な環境を提供したいと考えたのです。
──HWCを分社化したことで、どのようなメリットを感じていますか?
非常に大きなメリットを感じています。ヘッドウォータースの一部署として存在していた場合と比べて、はるかに大きな成長を遂げることができました。一般的にデジタルコンサルティング市場の年平均成長率は約20%と言われていますが、私たちは設立以来、毎年60%を超える成長を続けています。
正直なところ、分社化の当時はかなり慌ただしくて、細かいことはあまり覚えていないんです(笑)。でも、あのときに思い切って一歩を踏み出したからこそ、今の私たちがあると確信しています。

──高成長を支える「HWCだからこそ提供できる価値」は何だと考えていますか?
私たちはコンサルティングとテクノロジー活用を掛け合わせ、お客様が「これまで成し得なかったことを共に実現する存在」です。単に提案するだけでなく、テクノロジーを駆使してお客様とともに社会へ新たな価値を実装することが私たちのミッションです。
このミッションを実現できる理由は、ヘッドウォータースグループとの密接な連携にあります。技術の最前線にいる彼らと日々コミュニケーションを重ねることで、知識だけでなく、開発現場で得られる「何ができて、何ができないか」「どんな条件で失敗するか」といった、リアルで実践的なノウハウがグループ内に自然と流通しています。
こうした“空気のように触れられる実践知”こそが、HWCの大きな強みです。理論だけではなく、現場感覚に根ざした知見を持つことで、より確度の高い提案と実行が可能になっています。
パーパスに込めた想い。
「コンサルティングのない世の中」を目指して
──HWCは「新結合の社会実装」というパーパスを掲げています。これにはどのような想いが込められていますか?
HWCが掲げるパーパス「新結合の社会実装」には、私たちの根本的な想いが込められています。その出発点は、ある日ふと浮かんだ「コンサルティングを世の中からなくしたい」という言葉でした。少し過激に聞こえるかもしれませんが、これは私自身の本心でもあります。
この業界に長く身を置く中で、「コンサルティング」に対してネガティブな声を耳にすることがあります。たとえば「費用対効果が見合わなかった」「結局何をしてくれたのかわからなかった」「計画だけで終わり、実行が伴わなかった」といった声です。こうした声があることを知るたびに、私たちは「本当にこれがあるべき支援の形なのだろうか」と問い続けてきました。もちろん、すべてのコンサルティングがそうだとは思いません。しかし、少なくとも私たちは「今のコンサルティングのままで十分だ」とは考えておらず、もっと本質的にな支援の形があるのではないかと模索してきました。
その探求の中で出会ったのが、経済学者シュンペーターの「イノベーション=新結合」という概念です。彼は、革新とは単なる技術革新ではなく、既存の技術や知識、アイデアを新たに組み合わせることで生まれるものだと説いています。この考え方に触れたとき、「これこそが私たちの目指す姿だ」と強く感じました。お客様とテクノロジー、コンサルティングとテクノロジー──異なる要素を組み合わせて新たな価値を創出し、それを社会に実装する。提案や計画で終わらせず、実行までやり遂げる。その決意を「新結合の社会実装」という言葉に込め、私たちのパーパスとして掲げています。
──「新結合の社会実装」を実現した具体例を教えてください。
最近の事例としては、大和証券様や西日本旅客鉄道(JR西日本)様とのAI活用プロジェクトが挙げられます。これらの取り組みは、日本マイクロソフト社の公式レポートでも紹介されるなど、社会的にも注目を集めています。
大和証券様とのプロジェクトでは、生成AIを活用した「AIオペレーター」を導入し、問い合わせ対応の効率化を図るとともに、顧客体験の質的向上を支援しました。単なる業務改善にとどまらず、金融業界における顧客接点のあり方そのものを再定義する取り組みとなりました。
一方、JR西日本様とのプロジェクトでは、鉄道業界に特化したAIエージェント「Copilot for 駅員」を開発しました。駅員の業務負担を軽減しながら、利用者へのサービス品質向上を目指していました。現場のリアルな課題に寄り添いながら、テクノロジーを実装することで、公共交通の未来に貢献する取り組みとなっています。
これらの事例は、テクノロジーとお客様の事業を「新結合」させ、社会に実装するという私たちのパーパスを体現する好例です。単なる技術導入ではなく、事業の本質に踏み込み、社会に機能する形で価値を創出する──それがHWCの目指すコンサルティングのあり方です。

「少し外れた存在」──HWCで活躍する人物像とは
──HWCに在籍する社員に共通する特徴はありますか?
HWCには、新しいものへの好奇心が強く、変化を前向きに捉える方が多く集まっています。安定よりも変化の最前線に身を置くことで、より高いパフォーマンスを発揮できるタイプの人が多い印象です。単なる「新しいもの好き」ではなく、1つのことに粘り強く取り組む姿勢を持ちながらも、常に挑戦や刺激を求める意欲的な方が多いのが特徴です。
多くのお客様を支援する中で、接する方々の優秀さには日々感銘を受けています。その一方、変革のフェーズにおいては、そうした優秀さとは異なる視点やアプローチを持つ「少し外れた存在」が必要になる場面もあります。その対比の中で自社を見つめ直したとき、「私たちこそがその“少し外れた存在”として、変革を後押しする役割を担っているのではないか」と強く感じるようになりました。
──採用において重視しているポイントは何ですか?
私たちが採用で最も重視しているのは、パーパスやカルチャーへの共感、つまり「カルチャーフィット」です。スキルは入社後に身につけることができますが、価値観や人としての特性は簡単には変えられません。だからこそ、シンプルに「HWCに合う方かどうか」を大切にしています。
その判断軸として特に意識しているのが「ホスピタリティ」です。ロジックだけでは解決できない課題に向き合う場面が多いからこそ、お客様の取り組みに対して好奇心を持てるか、この人になら話してみたいと思っていただけるか、そして「人の役に立ちたい」という気持ちが仕事の価値観の中で上位にあるか等の姿勢を重視しています。
変化を仕掛ける組織の「変わらない」軸。経営者としての哲学
──代表として、組織マネジメントで大切にしていることを教えてください。
イノベーションを追求する組織である一方、組織マネジメントにおいては、私は原理原則を非常に大切にしています。変化の激しい時代だからこそ、パーパスという旗を高く掲げ、ミッションという軸をしっかりと持ち、そこからブレないことが重要だと考えています。具体的な組織設計やマネジメントの手法についても、グレイナーの成長モデルなど、時代を超えて支持されてきた古典的な理論を参考にしています。流行に流されるのではなく、普遍的な考え方に基づいて組織を築くことが、長期的な成長につながると信じています。
私たちは、お客様とともに常に変化に挑む存在です。だからこそ、社内には安心して立ち戻れる「変わらない土台」が必要です。原理原則に支えられた組織は、社員にとっての拠り所となり、結果として高いパフォーマンスを生む環境になると考えています。
──経営において特に重視しているKPIは何ですか?
まず前提として、KPIは多すぎると本質を見失いがちになるため、指標の数は絞り込むようにしています。その中で特に重視しているのは、提供価値の総量を示す「売上」と、事業活動の効率性を測る「営業利益」の成長率です。市場の平均成長率を大きく上回る「年率50%増」を、私たちの最低ラインとして設定しています。ただし、成長率だけを追いかけると組織のバランスを崩すリスクもあるため、財務面の健全性にも目を配っています。流動比率や負債比率など、経営の安定性を示す指標も定期的に確認し、持続可能な成長を目指しています。
また、事業視点で特に重視しているのが「派生率」です。これは、同じお客様から新たなテーマでご依頼いただく割合を示す指標であり、私たちの仕事が一度きりの支援ではなく、継続的な信頼と挑戦の連鎖につながっているかを測るものです。「派生率」が高いということは、私たちの支援が単なる提案にとどまらず、お客様の変革を本質的に支えている証でもあります。この継続性こそが、HWCの存在意義を示す重要なKPIだと考えています。

最後に
──会社の未来像と、そこで社員がどのようなキャリアを歩み、成長していけるのかについてお聞かせください。
私たちの会社が5年後、10年後にどうなっているかを正確に描くことはできません。というのも、今まさにコンサルティング業界は、AIの進化によって大きな変革期を迎えているからです。実際、これまで人が担っていたリサーチやレポーティングといった業務の一部は、すでにAIに置き換わりつつあります。
だからこそ、私たちは「新たなコンサルティングの形とは何か」を問い続け、その答えを実績とともに社会に提示できる存在でありたいと考えています。変化の激しい時代において、HWCは急速に成長を続けており、それに伴ってコンサルタントに求められる役割やスキルも進化していくでしょう。私たちは、その変化の先頭に立ち続けたいと思っています。
そして、会社の成長はそのまま社員一人ひとりの成長機会の広がりでもあります。私自身も、会社のステージが変わるたびに未経験の領域に挑戦してきました。同じように、社員の皆さんにも新しい役割やチャレンジの機会をどんどん提供していきたいと考えています。私たちがKPIとして「派生率」を重視しているのも、そうした背景があります。ひとつの業務にとどまらず、常に新しいテーマや領域に挑戦し続けることが、個人の成長にもつながると信じているからです。
正直に言えば、まだキャリアパスが完全に整備された環境とは言えません。しかし、だからこそ、変化し続けるこの環境にワクワクできる方、未来を一緒に形づくっていきたいと思える方にとって、HWCはきっとフィットする場所だと思います。
──この記事を読んでくださった求職者の方へ、メッセージをお願いします。
いまの私たちと、まだ見ぬあなたが組み合わさることも、まさしく「新結合」です。ITやコンサルティングの経験は問いません。むしろ、まったく異なる領域で培った知見や視点こそがこれまでにない新しい価値を生み出す可能性を秘めていると、私たちは信じています。
もし、私たちの考え方に少しでも共感していただけたなら。そして、変化に対して不安よりも「ワクワク」が勝るのであればぜひHWCの扉を叩いてみてください。あなたとの新しい組み合わせが、次のイノベーションのきっかけになることを、心から楽しみにしています。